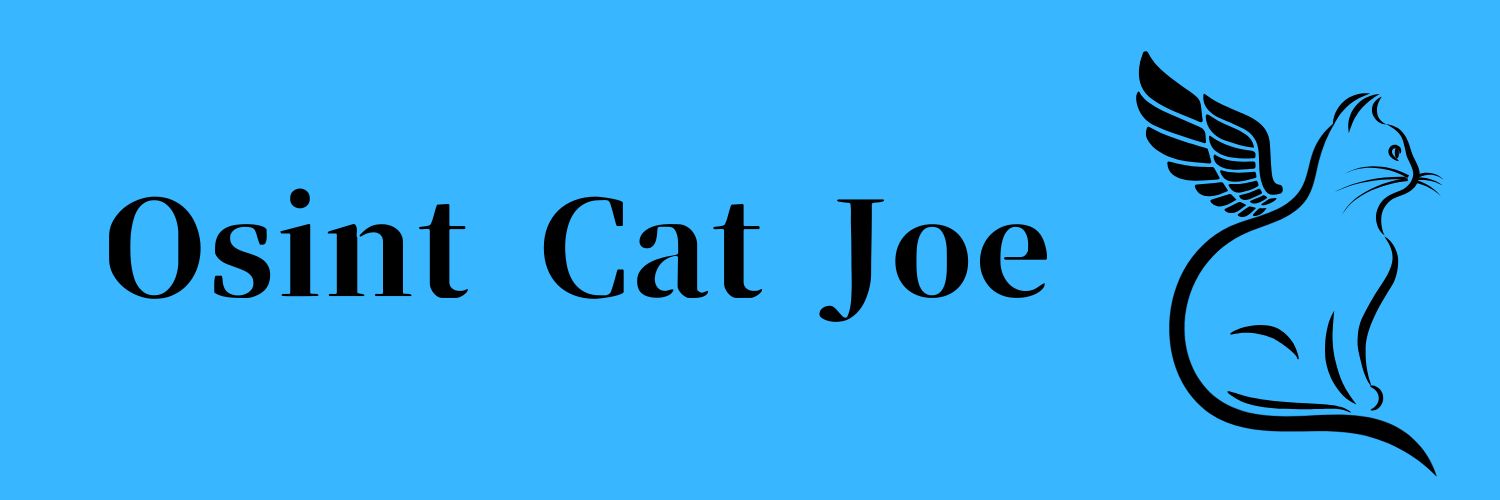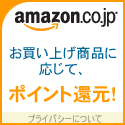【飛行機の基礎知識】戦闘機の「世代」とは?

こんにちは!
じょーです!
ニュースを見ているとたびたび戦闘機の「世代」についてたびたび注目されてますね!
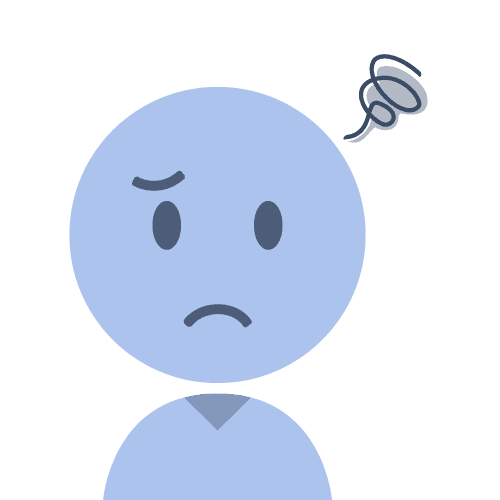
でも、「第〜世代」と言っても何が違うの?そんなにすごいの?
よく、「第5世代戦闘機はやっぱりすごい!」という意見が出ますが、このように世代ごとに何が違っているのか気になりますよね?
そこで今回は、そんな戦闘機の世代について特徴や代表する戦闘機にまとめました!
戦闘機の「世代」とは?
戦闘機の世代についてもともと決まった定義は存在しませんでした。初めて「〇世代戦闘機」という言葉を使ったのはロッキード・マーティン社とアメリカ海空軍だと言われています。
これは、現在量産中のF-35やF-22などの戦闘機をマーケティングする際、「第5世代戦闘機(Fifth Generation Fightr)」と呼び、商標登録までしたことで第5世代戦闘機はコレだ!ということが決まってしまいました。

そうなると、「それまでの世代はどうなっているの?」ということで後付けでそれまでの世代が定義づけされていきました。
この世代の定義づけについて何を基準にされたのかというと、明確な基準は存在していません。
しかし、月刊Jウイングで軍事評論家の井上考司氏は「飛行性能」、「探知性能」、「各種武器の性能」、「自衛性能」の4つを軸に分けられると言及しております。
ちなみにこの世代は第2次世界大戦集結後に生まれた戦闘機に対して区分けされています。
第1世代戦闘機
第1世代戦闘機は1950年代前半に誕生し、それまで主流だったレシプロエンジンをジェットエンジンに変えて飛行性能を向上させました。これに伴い、それまでは当たり前だったプロペラがなくなりました。
ジェットエンジンに変えることで特に高速化が進みましたが、エンジンの開発が現在に比べると未熟だったので比較的ずんぐりとしたフォルムのエンジンが大半でした。
そのせいか、当時開発された戦闘機の多くは機首に大型の空気取り入れ口を備えています。

また、戦後ドイツ人技術者がもたらした後退翼を採用する航空機が誕生し、それまで横一直線に伸びた主翼から後退翼がついた戦闘機が特に活躍しています。
この時の戦闘機はレーダーを搭載しておらず、主な武器は機銃ということで基本的には戦時中と同じように接近戦での戦いがメインでした。

第1世代戦闘機の代表的な機種
第1世代戦闘機は各国で開発され、主な機種はF-86やMiG-15など次のとおりです。
第2世代戦闘機
第2世代戦闘機は1950年代後半に誕生し、その特徴は「超音速飛行」ができることと、「レーダーを搭載した」ことの2点が大きく変わったところです。
特に当時は大型爆撃機の核兵器搭載能力が特に重要視されている時期でもあり、戦闘機を開発する際、爆撃機をより早く迎撃することを要求されることがその背景とされています。

最高速度と上昇性能を追求したため、全般的にスマートで鋭い近未来的なフォルムの機体がよく開発されました。
また、より遠くで目標を捕捉するため、レーダーが進化し探知距離が向上と小型化をすることができたので、現在の戦闘機では当たり前となったノーズにレーダーを収納するスタイルが確立されました。
第2世代戦闘機の代表的な機種
第2世代戦闘機はアメリカの「センチュリーシリーズ」をはじめ、各国で個性的な外見の機種が特徴的。
主な機種はF-104やMiG-21、ライトニングなど次のとおりです。
第3世代戦闘機
これまでの世代の戦闘機は主に速度性能をメインとした飛行性能の進化で分けられていましたが、第3世代では主にセンサーと武器が進化しました。
レーダーも対空目標のみ対象として追尾していましたが、対地攻撃も可能となりました。

また、レーダーホーミングミサイルが出現したことで目視外から攻撃できるようになったため、第3世代戦闘機はより多くのミサイルや、高性能のレーダーを搭載できるよう機体の大型化やエンジン性能の進化が求められました。
第3世代戦闘機の代表的な機種
第3世代戦闘機の主な機種はF-4ファントムⅡやMiG-25など次のとおりです。
第4世代戦闘機
第3世代戦闘機は多くの兵器搭載量を実現しミサイルの性能に頼りきる傾向となりました。その代わりにそれまでの戦闘機で重視していた軽快な運動性能を犠牲にしてしまいました。
特にベトナム戦争ではそれが顕著に表れ、特にアメリカの最新戦闘機はドッグファイトで負けてしまうことが度々発生しました。

そのため、第4世代戦闘機はこれまでのセンサー技術の進化もさることながら、運動性や加速性を追求し飛行性能の向上も主眼に置かれて開発しています。
飛行性能はこの世代でほぼ頭打ちになり、以後開発される戦闘機は第4世代戦闘機に似たフォルムとなっています。

これまでは兵器管制官を乗せて火器管制と操縦を分業させる戦闘機もいましたが、コンピューターが発達し、火器管制がより簡単にすることができるようになりました。
つまり、1人で対空・対地両方の戦闘を容易に切り替えることができるようになったことも特徴の一つです。
第4.5世代戦闘機
この戦闘機は、第4世代戦闘機と後述する第5世代戦闘機の間を指す戦闘機の一群を指します。
それまでの第4世代戦闘機をベースとし、主にコンピューターやセンサーをアップグレードすることで、限定的に第5世代戦闘機と同等の能力を持たせたものです。

第5世代戦闘機はステルス性が大きな特徴ですが、価格が高く輸出規制も非常に厳しく、購入には外交上の関係性も重要になるなどハードルが非常に高いです
第4.5世代戦闘機は、既存機のアップグレードで済む場合もあるので、コストパフォーマンスなどが高い選択肢になります。

第4+4.5世代戦闘機の代表的な機種
第4及び4.5世代戦闘機の主な機種はF-15やSu-30、ラファールなど、現在の主力戦闘機がそれにあたります。
第5世代戦闘機
現在、最強と言われる部類がこの第5世代戦闘機。
進化したところは「ステルス性」と「センサーフュージョン能力」がもたらした「相手に悟られる前に倒す」能力です。

見た目は第4世代戦闘機までと似ていますが、ステルス性を備えるためにこれまでのなめらかな曲線で構成された外見よりも角ばった外観をしています。
また、レーダーだけでなく赤外線センサーなどのセンサーやデータリンクをはじめとした通信も拡充され、より多くの情報を得ることができます。
さらに、取り込んだ多くの情報をコンピューターが自動で取捨選択し、パイロットは操縦に専念できるよう工夫されています。
第5世代戦闘機の代表的な機種
第5世代戦闘機の主な機種はF-35やF-22など、第4世代機から置き換わっています。
ただし、ステルス性を確保するための製造方法などは秘匿性やコストが高く、多くの国が開発できていないところが現状です。
第6世代戦闘機
まだデビューした戦闘機はありませんが、既に開発が始まっています。
それが、日本・イギリス・イタリアの3カ国で共同開発をしている「GCAP(ジーキャップと発音)グローバル戦闘航空プログラム」と先日アメリカで発表されたF-47です。

それぞれの機体は程度しか概念図しかありませんが、ただしその概念図を見ると第5世代戦闘機のようにステルス性を意識したデザインとなっています。
また、他の戦闘機や早期警戒機だけでなく無人機などともネットワーク上で繋がることで、より広い範囲で様々な作戦が遂行できるようになるとされています。
ただし、情報量が増えるとパイロットの負荷も大きくなります。
そこで、レーダーなどで探知した目標をディスプレイに表示するなど、直感的に情報を得られるよう工夫する取り組みがすでに始まっています。
なので、外見も未来的になりますがより重視されているのは、その機体に備えるセンサーやコンピュータの処理能力などのようです。
おわりに
第6世代機の開発の影響で改めて「戦闘機の世代」に注目が集まっています。
各世代ごとの戦闘機をご覧いただくと、時代ごとに特徴的な外観をしていて、その当時求められていた性能などを伺うことができます。
個人的には、世代が進んでいく毎に見た目の個性がなくなりつつあるところに悲しさを覚えますが、その裏側に求めた能力を伺うとやはりすごいなと感心するばかりです。
※ちなみに見た目では第2世代戦闘機のF-104が私のお気に入りです。

戦闘機という飛行機は、純粋に機械として性能の限界を追い求めて作られています。
ただし、その性能は様々な面で人間の限界を超えてきました。
そのため、今後生まれる戦闘機は、性能の向上と併せてパイロットの負担軽減策が今まで以上に重要になっていくと個人的には考えています。