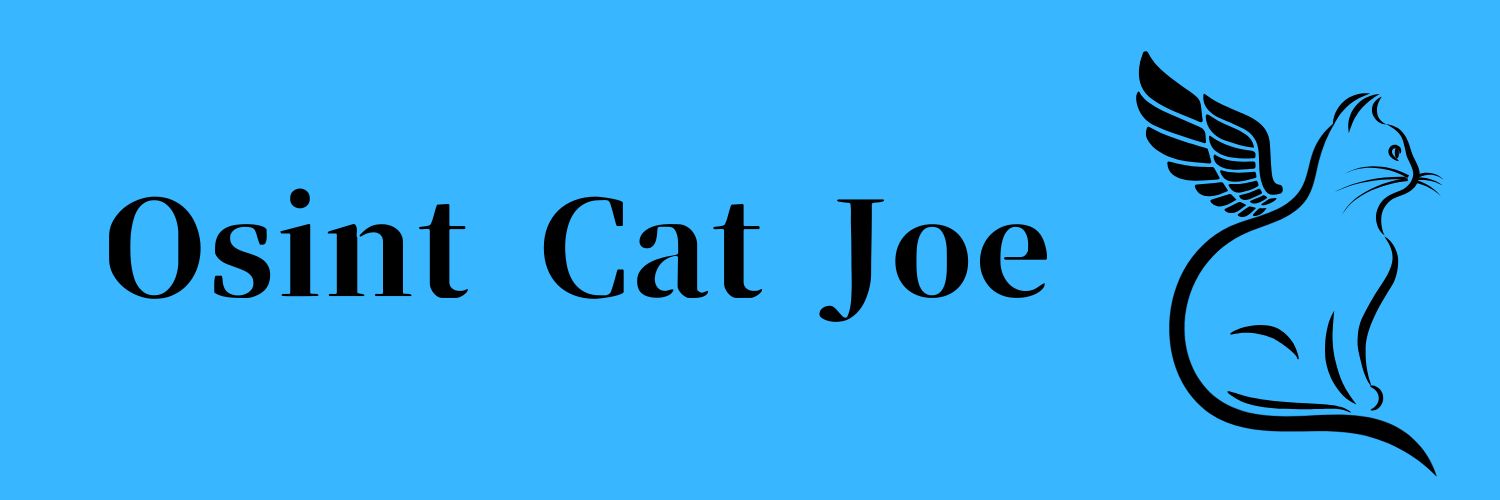【兵器解説】巡航ミサイル「トマホーク」とは?
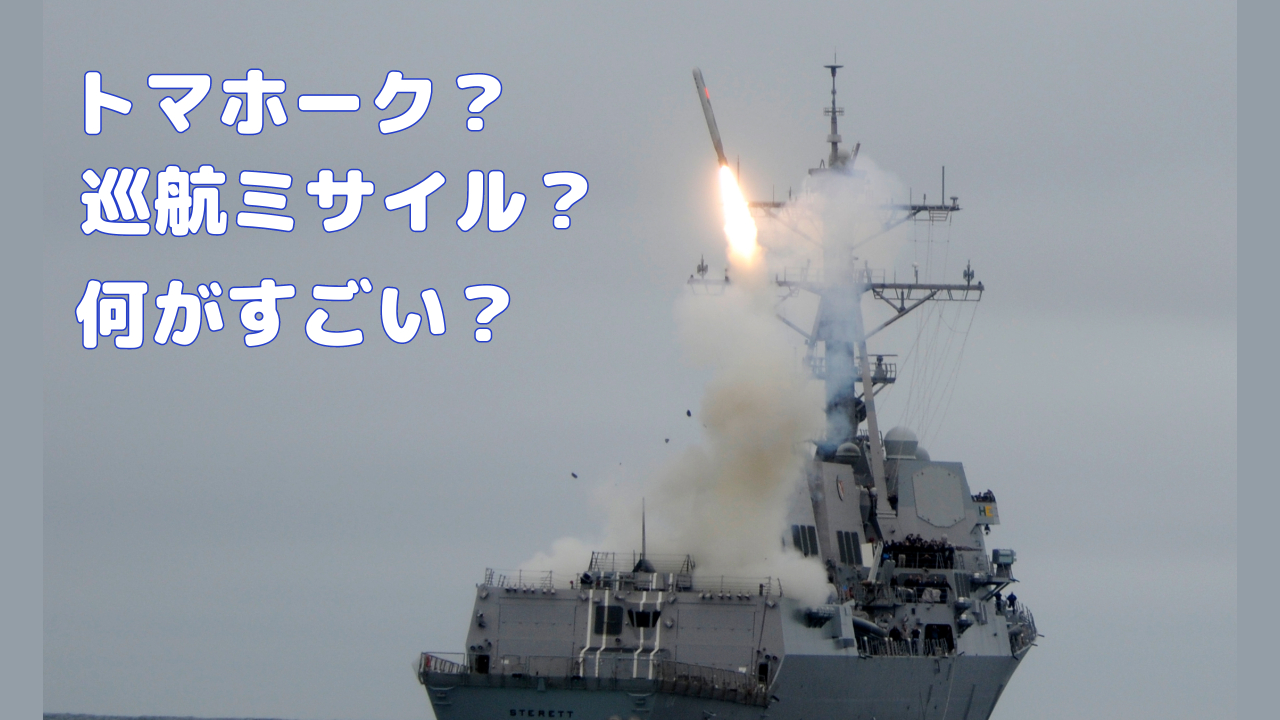
こんにちは!
じょーです!
今回は、ニュースなどで注目されている巡航ミサイルのトマホークについて解説します。
ミサイルという認知はない方も「トマホーク」という名前は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は「巡航ミサイルって何?」、「トマホークってどこがすごいの?」といった疑問に焦点を当て解説します。
巡航ミサイルとは?
巡航ミサイルは一般的に「飛行機のように長距離を自立飛行し、地上などにある目標へ攻撃するミサイル」を指します。
そのため、外見上の特徴として飛行機のように翼とエンジンを備えています。
また、非常に長い距離(基本的には1,000km以上のものが多い)を飛行するため、巡航ミサイルにはロケットモーターではなく、小型のジェットエンジンが搭載されています。(発射時のブースターとしてロケットモーターを搭載していることはありますが、ジェットエンジン点火後は投棄されます。)

同じく長距離を飛行するミサイルで「弾道ミサイル」がありますが、これは巡航ミサイルと比較すると1発の威力は大きいですが大柄で高価なので、運用面で柔軟性が非常に欠けます。
弾道ミサイルに関する詳しいお話は下記の記事にて紹介しております。

トマホークについて
それでは、トマホーク巡航ミサイルについて説明します。

トマホークの正式名称は「RGM/UGM-109」といい、「RGM~」は艦上発射型、「UGM~」は潜水艦発射型で発射する乗り物によって少し名前が異なります。
アメリカのレイセオン(現RTX)社で製造しており、アメリカ海軍とイギリス海軍が運用しているほか、カナダ・オーストラリア・オランダが現在日本と並び導入計画中です。
ちなみに、「Tomahawk(トマホーク)」という名前はアメリカの政府機関である海軍省の登録商標となっています。
トマホークのスペック

| 全長(ブースター除く) | 5.56m |
| 翼幅 | 2.67m |
| 直径 | 0.52m |
| 速度 | 880km/h |
| 射程 | 900NM(約1,670km) |
| 誘導方式 | TERCOM、INS、GPS等 |
全長が5.5mというと、車のハイエースよりすこし長いくらいの大きさです。やはり、長距離を飛ぶために必要な燃料や複雑なセンサーを組み込むと大きくなるようです。
火薬が入っている弾頭部には、1000lbs(約450kg)の高性能爆薬またはクラスター爆弾と同じタイプの子弾ディスペンサー(小さい爆弾)が約170発入っています。
トマホークのすごいところ
トマホークは約1,670kmもある長い射程がスペック上の最も大きな特徴です。
これは大阪から台湾くらいの距離で、自衛隊の護衛艦などが活動する日本海や東シナ海からだと中国や北朝鮮、ロシアの主要な都市をカバーできます。

さて、そんな遠いところまで飛べるトマホークですが、最もすごいところはそれほど遠いところへ極めて正確に命中させることができるところです。
その正確性はCEP(Circular Error Probability:平均誤差半径)が10mと言われております。
これは、例えば10発発射した場合、その半数以上が目標の10m以内に着弾することを示しています。
ここまで正確に誘導できるのは、トマホークを誘導するために利用するセンサーや、誘導方式に秘密があります。
トマホークでは、TERCOM(地形輪郭マッチング)という誘導方式をデビューした1980年代から採用しています。これは、事前にデータ収集した地形データを発射前に入力して、飛行しながらそのデータを測定・比較しルートを確認しながら誘導する方式です。
つまり、事前にコースを設定して発射したらあとは勝手に目標まで飛行するので、着弾するところを見守るだけになります。
1990年代からはGPSが実用化され、座標データと高度情報をさらに照合させることで正確性が向上し、さらにそれまではできなかった「飛行中のルート変更」ができるようになりました。

そのため、発射前のデータになかった障害物などを回避することができるようになり、撃墜される確率が低下しました。
また、個人的には世界中の地形データを収集している米軍も非常にすごいなと感じました。この地形データこそトマホークの要となりますので、当然トマホークを売るとなるとこのようなデータも併せて手に入れることができるはずです。
・射程が長い(大阪から台湾までの距離とほぼ同じ!)
・正確性が高い(外れても目標の10m以内に着弾する)
・事前にコースを設定したら勝手に目標まで飛行する→その間に自分は移動できる。
進化を続けるトマホーク
トマホークは前述した通り、主に艦艇や潜水艦から発射されますが、現在陸上発射型が開発されており実証試験中です。
これは主にアメリカ陸軍が担当しており、大きなトレーラーにミサイルを入れたコンテナ(業界用語で「セル」と呼んでます)を入れ、発射するときはセルが上に向き発射体制に入ります。
これは、艦艇に搭載されているVLS(垂直発射装置)を専用のトレーラーで運び、発射位置に着いたらセルを上に向けてミサイルを発射するというコンセプトです。
従来のセルを転用できるので、比較的リーズナブルに作ることができると思われます。(陸上発射にする分、システムなどを再構築すると予想されますが・・・)
この発射実験は2023年6月に成功が発表され、引き続き実験中とのことです。

弾道ミサイルとの違い
スペックを見ていただくと「弾道ミサイルより速度が遅いから撃ち落される確率が高いのでは?」という疑問が湧く方もいるかと思います。
それは技術者も開発時点で分かっていることなので、「どうやって長距離を飛行している間に撃ち落されずに目標へ辿り着くのか?」という課題に対して「レーダーに探知されないくらい低い高度を飛び続ける」という答えに辿りつきました。
ちなみにトマホークの飛行高度は対地30~50mと日本の一般的なタワーマンションの真ん中くらいの高さで飛行します。そのため、トマホークは地表を飛行するときは物陰に隠れながら目標まで近づいていくのです。

つまり「安全地帯から発射して、相手にバレることなく攻撃する」ことがコンセプトになります。
対する弾道ミサイルは、その威力と落下速度で「捕捉できても迎撃ができない」、「直撃しなくても大ダメージ」という状況を作り出します。位置がバレたりしてもマッハ5以上で落下し町1つを消滅させるだけの威力を持っているので、発射して再突入さえできればなんとかなってしまいます。
しかし、ミサイルそのものの大きさや発射装置など全てが大掛かりでコストが高くなるところが欠点の1つです。
弾道ミサイルはニュースでもご覧のとおり「爆弾を乗せた宇宙ロケット」のようなものなので発射台も大掛かり、発射までの準備やミサイル本体の整備が繊細で時間がかかるなど、作ることも維持することも非常にコストがかかります。
・巡航ミサイルの方が命中まで相手に見つかりにくい
・弾道ミサイルの方が威力は大きい
・弾道ミサイルの方が何かとお金がかかる(コスパが悪い)
自衛隊が導入できることはすごいこと
さて、ここまではトマホークというミサイルのすごいところを紹介しましたが、ここでは自衛隊が導入できることがどれほどすごいのか簡単に解説します。
先程も触れましたが現在運用しているのはアメリカとイギリスになります。
この2カ国が非常に深い関係であることは皆さんご存知かと思いますが、トマホークが運用できることに関してその点も実はその点も関係しています。
なぜなら、目標となる地点の地形データなどを正確に収集できる能力を保有し共有するには相応の関係性がなければいけません。そのデータはアメリカなどが様々な方法を駆使して得た門外不出のデータです。それを誰にでも渡すほどアメリカもお人よしではありません。
また、トマホーク自体はアメリカから購入しますが、そのためにはアメリカの議会承認などを経て輸出許可が出ますので、外交分野でも相当の努力が必要だった思われます。
当然、アメリカ製の防衛装備品に関する情報漏洩などの不祥事が発覚すると、この契約は破棄される可能性があります。(以前、航空自衛隊へF-22ステルス戦闘機の輸出がアメリカで検討されていましたが、イージスシステムに関する情報漏洩が発覚し破棄されたことがあります。)
また、トマホークはミサイル自体を買って護衛艦に搭載したら使えるのではなく、ターゲティングを行う(狙いを定める)システムの追加や、地形データの取得など様々な準備が必要です。
一部の意見では国産ミサイルの実用化までの「つなぎ」という方もいますが、私はそこまで苦労して取得できた実績豊富なミサイルをつなぎにするようなもったいないことはしないと予測しています。

おわりに
今回は自衛隊への導入が決定したトマホークについて解説しました。
米軍が空爆を行う際必ずニュースで紹介されますが意外に馴染みがなかったのではないでしょうか?
自衛隊への導入が決まり注目度が高まっていますが、これが実現した背景は当然世論の影響が大きいです。
その効果は既に出ており、中国が「防衛3文書」を発表した後に日本へ批判したことで「脅威と感じている=抑止力を持ち始めた」と認識しています。
このような兵器を導入しようとするとどうしても「戦争が発生する可能性を助長している」という意見がございますが、一般的にその武力を「他国の主権を犯そうとすること」に使うことはありません。
それは、国連憲章や日本国憲法にも記載されているとおりで世界の一般的な共通認識です。
しかしながら日本周辺の中国・ロシア・北朝鮮は自国の利益のみを優先するように見受けられるため、平和を築く世界的な努力を砕こうとしているとみられているのです。
なので、実際に日本の主権が脅かされる事態が起きてはならないようにすることと、万が一起きた場合の備えを始めたにすぎません。
防衛政策に関しては、防衛省のHPや防衛白書に記載されていますので、興味のある方は是非ご覧ください!